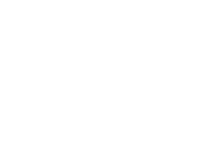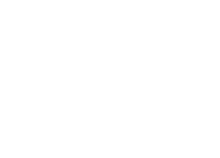ありえない、仕事
土と鳥と自分のために種を蒔く-人生の哲学が詰まった「農業」という選択
自分で野菜を育ててみたい。そう思いながらも、始めるには畑の確保や道具集めなど、入り口に立ちはだかる壁の高さに、「いつか…」で止まっているという方も多いのではないでしょうか。
今回取材に伺った「みつぶ農園」の笠原さんは、縁あって農業の道へ進み、移住した信濃町で育てた野菜を販売されています。
哲学的な視点を持ち農業はあくまで一つの手段として、自然体で向き合う生き方に、「やりたい」と「難しい」の間で揺れ動く人にとって、背中を押すきっかけが見つかるかもしれません。
今回インタビューした方

笠原智薫さん
長野県長野市出身。大学進学を機に愛知県へ出た後、祖父の土地を継ぐタイミングでUターン。農業研修等を経て、2024年に信濃町で「みつぶ農園」を独立開業し、妻と保育園に通う息子の3人で暮らしている。
小学生での授業が農業の原体験に

農家として独立して2年目。実家が農家という訳でもなく、以前は虫も触れなかったという笠原さん。記憶を辿ると、そこには小学校での体験がありました。
「低学年の時に担任の先生がユニークで、教科書をあまり使わず、自然の中で遊ぶような授業をしていました。クラスで飼っていた羊の毛刈りや出産の立ち合い、堆肥づくりも自分たちでやっていました」
感性豊かな時期に五感を使って学んだことは、小学校6年間の中でも特に強く思い出に残っています。担任が変わるとそうした体験からは離れ、再び自然と近づくことになったのは、進学先の愛知県で事務職に就いて2年ほど経った時のことでした。
故郷への回帰、そして運命的な再会

きっかけは、祖父の農地と山林を継ぐという話から。「いずれ長野に戻りたい」と思っていたこともあり、人生の岐路とも思えるその大きな選択を受け入れたことが、笠原さんが農業の道へと進むきっかけになりました。
「せっかく土地があるなら活用したい」と信濃町のキャベツ農家の元でアルバイトを始め、次第に有機農業に関心が向いていったと言います。
有機農業が学べる受け入れ先農家を探し、見つけたのが小川村にある「まごころふれあい農園」。実は、その農園を主宰する久保田清隆さんが、小学生の時にクラスのみんなで堆肥作りを教わりに行った農家さんだったのです。はじめはお互い気が付かず、たまたま研修先の話をした母が覚えていて分かったのだとか。
かくして再び数年越しのご縁が繋がり、有機というアプローチにますます確信を得た笠原さんは、アルバイトを辞め、県の助成制度を利用し農業研修生として久保田さんの農園で働くことになりました。
「もともと独立意欲はありました。何でも自分で一から決めて自分の責任でやりたいと思っていて、せっかくなら生活の根底にあるようなことに関わりたい、地球にいるなら地球や自然に関わりたい。農業に行き着いたのもそんな思いからでした」
当時、久保田さんの農園では2〜3ヘクタール(サッカーコートに換算して3〜4面半くらいの広さ)に、多い時で100種以上の多品目を笠原さん含め4名ほどのスタッフで栽培していたそうです。
「農業をするために生まれてきたような人」だという久保田さんに、種播きや苗づくりだけでなく、自然由来の肥料づくりや野菜販売の営業まで、多岐にわたる農業のノウハウを学び研鑽を積んでいきました。
ご縁で結びついた信濃町での家と土地探し

研修期間の終わりが近づき、就農先を考えたとき、ふと脳裏に浮かんだのはアルバイト先で眺めていた信濃町の風景でした。
「北信五岳の広がる景色や、環境が良かったんです。子どもが生まれたばかりで自然の多い場所を考えていたし、電車が通っていて長野市へのアクセスもよくて」
久保田さんの農園からも、祖父から継いだ土地からも離れた、縁もゆかりもほぼゼロの場所でのスタート。家探しと畑探しからの始まりでしたが、ここでも幸運な流れに恵まれました。
助成を受けていた関係で役場にも顔見知りの職員がいたり、ちょうど1か月前くらいに売り出された空き家の話が舞い込んできたりと、トントン拍子に進んでいきます。
駅に近く、家の裏には畑もあり、笠原さん達が考えていた条件にぴったりの物件でした。2023年の末に購入を決め、リフォームを経て、翌年6月にいよいよ信濃町での暮らしが始まりました。
その間も栽培計画を立て、苗づくりなどの準備を進めていました。丁度、規模を縮小するタイミングだった久保田さんからハウスの部材を譲り受け、資材調達では周囲との関係にも恵まれました。
6月といえば、信濃町では雪どけ後の土のぬかるみがようやくおさまった頃。豪雪地帯の気候は、農業を営む上で不利な条件が多くありますが、それでも笠原さんが信濃町で農業をすると決めた理由には、町の特産品である「とうもろこし」の存在が大きかったと言います。

「どんな品種を育てるかを考える必要があると思いました。信濃町といえば、とうもろこしが有名だから、経営戦略的にもそれを中心に他にも何十種類か植える計画を立てました。商業作物として成り立つ、とうもろこしと米を組み合わせる農家さんもいます。土質が良好で、雪のない限られた期間でみれば、すごくいい作物ができる土地です。」
昨今は気候変動の影響もあり、雨不足や異常な暑さが作物の生育にとっては大きな打撃。農業で辛いと感じることは「人の手ではどうにもならない天候のこと」だと言います。
しかし、笠原さんから「辛い」「大変」というネガティブな言葉は一切聞かれません。厄介と思われがちな雪に対しても、笠原さんはポジティブに捉えます。
「土が見えていると何かしなきゃって焦ってしまうから、雪に覆われることで心が休まる面もあります。こういう閉ざされた空間にいて、雪を見ているのも好きです」
笠原さんは直面する出来事に対して、常に自分なりの最適解を冷静に見出し、自分が心地よい選択を重ねているという印象を受けました。
雪が降れば農作業はお休みになり、冬の間は会社員時代の経験を活かした仕事をこなしながら、合間に雪の下から掘り起こした野菜を出荷しています。雪があることで、野菜の甘みが増すことも雪国ならではの特権です。(立てておいた目印が埋まるくらい積もることもあるというから、信濃町に降る雪の量は推して知るべし、です。)
「みつぶ農園」の名前の由来と有機農業を選択する理由

どこか哲学的に感じられるその考え方の土台には、社会人まで続けていた合唱も一つの要素となっています。はじめは中学校の部活選びで、「歌が好きだな」というくらいの気持ちで入部した合唱部は全国大会に出場するような強豪でした。高校でも続けて、一時は音楽教諭の道を志したものの、練習するほど下手になる感覚があり教師の道は「合わない」と直感したそうです。
それから進路選択を迫られた高校3年生の頃には、「生きる意味」について考えるようになりました。
「どういう人生を歩もうか考えていました。哲学に興味がありましたが、より理論的に捉える心理学科へ進むことを決めました」
進学したカトリック系の大学では聖歌隊に所属し、神父でもある教授の指導に刺激を受け、当時は学業よりも歌に打ち込んでいたと言います。合唱といえば体力づくりが求められるイメージですが、笠原さんは「体の仕組みを知って使い方を考えながら取り組んでいた」そうです。
ともすると農業とは直接の関連性がなさそうに思える一連の経験や、選択の一つ一つが笠原さんを構成する要素になっていると感じたエピソードでした。
その哲学的な視点は、農園の名前にも反映されています。
「みつぶ農園という名前は、三粒の種ということわざから取りました。一粒は空を飛んでいる鳥のため、二粒目は土の中にいる虫のため、三粒目は自分たち人間のため、という自然共生観が自分たちの理想に合っているなと思ったんです」
笠原さんが大事にしているのは、「何でも自分でできる」こと。
自然の中にいるなら、なるべく自然に還元できる「手に届く範囲」を意識して、苗づくりや土着の菌を集めて培養する土づくりは、久保田さんの教えが生きています。
「久保田さんは、「悪い菌」はいなくて、菌が偏るから病気になったり野菜にとって悪い影響が出たりするのだと言っていました。多様な菌がいることで相互作用によってそれぞれが育つという考え方を教わりました」
「なぜ有機なのか」という答えはまだ探し中という笠原さん。

以前は触ることもできなかった虫は、今では「割と好きなレベル」にまでなりました。畑に出ていて虫との距離が近くなったことも影響しています。
引っ越した当初は自宅の一角で営巣する蜂に向けて殺虫剤を使っていたのが、畑でマルハナバチが胡瓜の花粉を体の両脇につけて運んだり蜜を吸ったりしている姿に出会ってから「もう薬を使うのは辞めよう」という境地に至ったのだとか。
かわいい蜂の姿を想像すると、「確かに」と共感を覚えます。(マルハナバチは毒性も攻撃性も低いと言われています)
笠原さんが作物の味や収量を求めるよりも自分の根幹に関わる部分で共鳴したのが有機農業であり、それはただの栽培方法に留まらず、自身の生き方に繋がっているようです。
食べてくれる人が喜んでくれることが原動力

みつぶ農園の野菜は、町内の道の駅や食堂や個人販売が主軸になっています。注文管理やウェブサイトの運用は笠原さん自身で行い、「何でも自分でやりたい」性分がここにも生きています。
「一から自分で作ったものを人に渡せて反応がもらえるのは、農業をやっていてよかったなと思う瞬間です」と笑顔で語る笠原さん。
なかでも評判が高いのが、とうもろこし。皮をむかないと中まで見えない点は見極めが難しく、1万本以上植えても収穫までいかなかったり小さいままだったりするなど、一筋縄ではいかないのは難しいところです。
その他、キャベツや大根、ニンジンなどの定番野菜から、珍しい品種にも積極的にチャレンジしています。例えば、「カリフローレ」は、カリフラワーをスティック状にしたような形で、カリフラワーより柔らかく、甘みが強いと聞いて試しに育ててみた品種です。
「割れやすいなどの理由で流通しづらい品種もありますが、もっと多様な品種を育ててみたいと試行錯誤しています」
例えば、雪どけ後にすぐ暑さを迎える信濃町の気候では冷涼地を好むセロリがうまく育たなかったなど、実践を重ねながら町の風土と合う作物を研究する日々。

そんな思いの詰まった美味しい野菜を食べられる息子さんはさぞ幸せ者だろうと思いきや、偏食気味なお年頃で、野菜をなかなか食べてくれないのだとか。それでも、「とうもろこしはもちろん、スイカをバリバリ食べてくれた時は、農業をやっていてよかったなと思いました」と話します。
息子さんに農業を継いで欲しいという気持ちはなく、逆に押し付けたくないと思っているそうです。
「なぜ有機なのか、という答えが出せていない自分のように、息子にも自分の生き方を自分で見つけてくれたらいいなと思っています」
息子さんが産まれたのは、ちょうど信濃町に移住するタイミングとほぼ同じ。大学で出会った妻とは長野へUターンすることが決まった時に結婚し、笠原さんがゼロから始めるかたわら、一緒にやってきました。

「何もわからない状態で、ゼロから色々と吸収しようとしている段階なのかなと感じています。今日も午前中、一緒に作業をしていました」
夫婦二人三脚で、今では共にみつぶ農園を支えるパートナーとして、信濃町の土と向き合っています。
町土づくりのように
信濃町では師匠もいないまま農業を始めた笠原さんですが、農家以外からも教わっていると言います。
「家庭菜園をしている人がたくさんいるので、種を播く時期を聞いたり、道すがら人の畑を観察したりするだけでも勉強になります。運転していてつい見ちゃいますね」と、地域の人々からも日々吸収しています。
「よく来てくれた、と温かく迎え入れてくれて、近所づきあいも良好なのはありがたいことです。みんな雪の大変さが分かるから、それを共有できるのかもしれません」
移住者同士の交流も活発だと言います。町に元から住んでいる人も移住してきた人も混ぜ合わさって豊かな繋がりを醸成している様子は、まるで、多様な菌を集めて培養して、野菜の栄養にしていく土づくりにも繋がっているようです。
これから農業を始めたい方に

もとは小学校での原体験から、自分の「好き」というシンプルな感情にしたがってきた笠原さん。農業は今や暮らしの一部になっています。
「人の健康とか幸せのために農業をしている人はすごい。自分たちはただ、こういう環境でやりたいなという思いでやっているだけで。でも、自分たちがやりたいと思うことをやれる、それが一番です」
「好きだけじゃいけない」という固定観念に縛られ生きづらさを感じている人が多いなか、笠原さんのメッセージは、「それでもいいよ」と肯定してくれているようです。そこにあるものを活かして、自分にとっての最善を選びとっていく有機農業のスタイルには、そんな優しさを感じます。
最後に農園の展望について尋ねると、
「信濃町の地域に合った野菜や、時期を見極めて、自然と仲良くなれたらいいなと思っています」と笠原さん。
みつぶ農園の可能性はこれから広がるばかりです。
笠原さんの哲学が詰まったお野菜を味わいながら、自分と向き合う時間を作ってみては?
おだやかな口調と優しい表情で話される笠原さん。つい人生から深掘りしてしまいました。取材に伺った時は残念ながらとうもろこしシーズン終了後。何万本と植えても天候次第で収量が半分以下ということもあるという貴重な宝物を、来シーズンは狙って買いに行きます!ありがとうございました。
みつぶ農園
ホームページ https://mitsubufarm.com/
Instagram https://www.instagram.com/mitsubufarm/